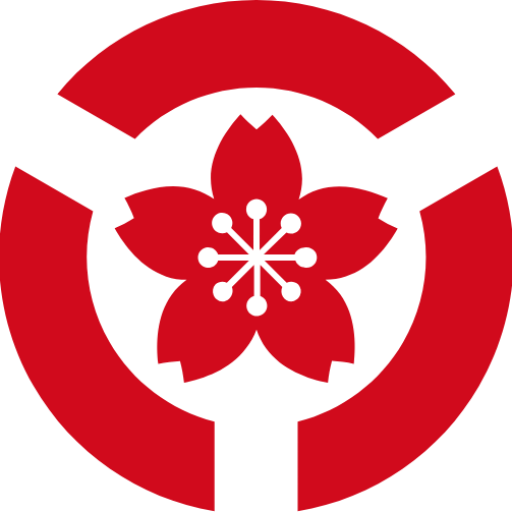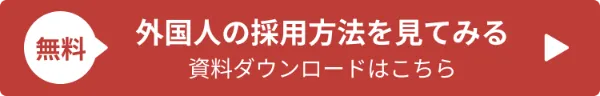厚生労働省は「外国人介護人材の働き方についての検討会」を開き、特定技能や技能実習生として働く外国人介護士が訪問介護をできるようにするかどうかを議論しています。地方での介護人材確保の課題や、新制度「育成就労」の導入によって生じる可能性のある問題についても触れており、今後の介護業界の動向を知りたい方にとって重要な内容となっています。
6月19日に厚生労働省は「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」を開催し、特定技能や技能実習の外国人材による訪問介護を認める内容などの中間報告が行われました。
この検討会は、2023年7月に政府の有識者会議が技能実習制度の廃止と新制度の創設を検討し始めたことを受けて議論を開始したもので、外国人が介護福祉士として働く事業所へのヒアリングも実施しました。
現在、特別養護老人ホームなどの施設では在留資格に関係なく働けますが、訪問介護に関しては、経済連携協定(EPA)締結国出身の介護福祉士や在留資格「介護」を持つ外国人しか従事できません。
今回の中間案では、ヒアリング結果などを基に、「介護職員初任者研修を修了している者」など、日本人と同様に一定条件を満たす外国人材による訪問介護を認めるべきだと提案されています。
具体的な条件としては、事業者に対して以下のことを求めています。
①訪問介護の基本事項や日本の生活様式を含む研修の実施
②一定期間の同行支援の提供
③キャリアパスの構築に向けた計画の作成
④ハラスメント防止のための対応マニュアルの作成
一方、6月14日には「技能実習法等改正法」が成立し、外国人の技能実習制度に代わる育成就労制度の創設が決定しています。この新制度は、労働力不足を補うための人材確保と育成を目的としており、同じ職場で1〜2年働き一定の条件を満たした場合、転籍(転職)も可能というものです。

全国社会福祉法人経営者協議会の外国人介護人材特別委員長である濵田氏は会合で、外国人が日本語を習得することの難しさについて言及しており、「一定の水準に達した人材の在留資格を延長し、人材の流出を防ぐ方法を検討してほしい。特に地方では人材の確保が難しい」と述べています。
全国老人福祉施設協議会の外国人介護人材対策部会長である中山氏も、「働く権利は認めるべきだが、地方から都市部への人材流入が多い現状で転籍を認めると、更なる問題が生じるのでは」と懸念し、国の支援の必要性を示唆しました。
また、全国介護事業者連盟の理事長である斉藤氏は、「特に訪問介護のヘルパー不足が顕著であり、事業者の倒産件数も増加している」と指摘し、早急な制度の実施を求めました。
(参考)特定技能、技能実習でも訪問介護認める 厚労省検討会が新方針‐福祉新聞WEB




新制度の導入に向け、政府は地方から都市部への介護人材流出を防止する制度を整える必要がありますね。訪問介護に従事できる外国人介護士の幅が広がることで、介護業界の人手不足が緩和されることに期待したいです。