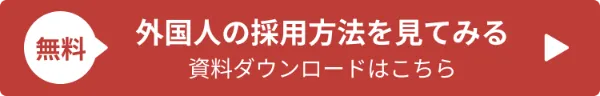インドは教育の質と規模の両面で世界的に注目されている国です。多くの優れた大学があり、その中には世界的に評価されている大学もあります。今回は、インドの大学ランキングと就職の可能性について詳しく見ていきましょう。

インドの基本情報
まずは、インドという国の基本情報を紹介します。
国名
インド共和国 / バーラト(Republic of India / BHARAT)
首都
ニューデリー(New Delhi)
地理
インドはアジア大陸の南部に位置し、インド亜大陸と呼ばれる大陸の一部を占めています。国土は非常に広大で多様な地形が広がり、ヒマラヤ山脈から始まり、ガンジス川平原、デカン高原、そして多くの海岸線があります。
人口
インドは世界で人口が最も多い国の一つで、2021年の情報によれば約13億人以上の人々が暮らしています。
公用語
インドには多くの言語が話されており、憲法で公用語として指定されている言語はヒンディー語と英語です。ただし、地域によってさまざまな言語が使用されています。
宗教
インドは多宗教国で、ヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教、仏教、ジャイナ教、シク教などさまざまな宗教が共存しています。ヒンドゥー教が最も多数派の宗教ですが、多くの宗教が信仰されています。
政府
インドは議会制民主主義国家であり、大統領が国家元首で、首相が政府の長です。議会は二院制で構成されており、人民院(ロク・サバー)と州政府代表院(ラージヤ・サバー)があります。
経済
インドは新興国として急速な経済成長を遂げ、多様な産業が存在します。情報技術、自動車産業、製薬産業、農業、繊維産業などが国内外で注目されています。
通貨
インド・ルピー(Indian Rupee、INR)が国の通貨単位です。
文化
インドは多様な文化、伝統、言語、宗教、料理、音楽、ダンスが共存する国として知られています。ボリウッド映画は世界的に有名で、インドの文化的な遺産も非常に豊か
です。
国名の変更(インド→バーラト)
2023年9月のG20サミットで、インドは議長国として主要20カ国・地域首脳会議に参加しました。この際、インドは自国の国名を「バーラト(BHARAT)」とすることを発表しました。この変更は世界に驚きをもたらしました。以前は外交の場で「INDIA(インド)」として知られていたためです。
この変更は、ヒンディー語におけるインドの意味である「バーラト」を尊重するもので、インド憲法においても「バーラトは、諸州の連邦である」と規定されています。従って、インドとバーラトという名称は憲法上どちらも有効なものです。
公式な説明は提供されていないものの、バーラトという名称はより古代の起源を持つため、植民地時代の印象を薄める可能性があります。また、この変更はヒンディー語を話すヒンドゥー教徒にとっては好意的に受け入れられるでしょう。モディ首相は、2024年の総選挙に向けてバーラトの使用を強調することで、国名変更を計画していると見られています。
インドは世界で最も人口の多い国であり、経済的にも急速に成長しており、国内総生産(GDP)は将来的には世界第3位になると予測されています。このような大国の国名変更は、さまざまな影響をもたらす可能性があります。
(参考)G20でインドの国名がバーラトに → 国の名前が変わることってあるの?|一色清の「このニュースって何?」|朝日新聞EduA
インド(バーラト)の教育制度と特徴
インドの教育制度は多様かつ複雑で、中央政府と州政府の両方が教育を監督・管理しています。ここからは、インドの教育制度について詳細に説明します。
学校教育と大学教育の特徴
①学校教育
学校教育はインドの教育システムの基本です。学校教育は幼稚園から12年生までの段階で提供されており、これを一般的に「K-12教育」と呼びます。
・幼稚園(プリスクール)
3歳から5歳までの子供を対象とし、基本的な認知スキルと社交的なスキルの育成が行われます。
・初等教育(プライマリースクール)
6歳から10歳までの子供を対象とし、基本的な学科(言語、数学、科学、社会科学など)が教えられます。
・中等教育(セカンダリースクール)
11歳から15歳までの子供を対象とし、より高度な学科が追加されます。
・高等教育(シニアセカンダリースクール)
16歳から18歳までの生徒が、高等学校卒業資格(10 + 2)を取得するための学校段階です。
②大学教育
インドには多くの大学があり、大学教育は大学とカレッジで提供されます。インドの大学教育は学部、修士、博士の段階で提供され、多くの専攻やコースが用意されています。最も有名な大学の一つはデリー大学、ボンベイ大学、カルカッタ大学、イムダードバード大学などです。
教育制度のその他の特徴
・公立と私立教育機関
インドには公立学校と私立学校が共存しており、私立学校は一般的に高品質な教育を提供していますが、学費が高いことがあります。一部の中央政府および州政府の学校は無償で教育を提供しています。
・言語
インドには多くの言語が話されており、各州で異なる公用語があります。英語は広く使用され、大学や専門教育機関では英語が主要な教育言語の一つです。
・教育制度改革
インド政府は教育制度の改革を進めており、特に新しい国民教育政策(National Education Policy)が導入されました。この政策は幼児教育から大学教育までの範囲でさまざまな変更を提案しており、技術教育や職業訓練の重要性を強調しています。
・受験競争
インドの教育制度は非常に競争が激しく、入学試験や大学進学試験は非常に重要です。特に、工学、医学、経営学の分野では競争が激しいです。
・教育の普及
インドでは教育の普及に向けた取り組みが進行中で、特に女子教育の促進や農村地域への教育の普及が重要な課題とされています。
インドと日本の教育制度の共通点
インドと日本の教育制度には共通点があります。ここからはその共通点を紹介します。
・義務教育制度
両国とも、基本的な学校教育を義務教育として提供しており、児童・生徒が一定の学年まで教育を受けることが法的に義務付けられています。インドでは8年間、日本では9年間が義務教育の対象です。
・試験制度
両国の教育制度では、定期的な試験や評価が行われ、生徒の進捗や成績が追跡されます。また、大学進学や進学校の入学試験など、競争の激しい試験も存在します。
・多段階の学校段階
インドと日本の教育制度は、初等教育、中等教育、高等教育など、複数の段階で構成されています。生徒は段階的に進級していく仕組みです。
インド(バーラト)と日本の教育制度の違い
インドと日本の教育制度には違いがあります。ここからはその違いを紹介します。
・学年の長さ
インドの学校教育は、一般的に12年制で、高等教育の前にシニアセカンダリースクール(10 + 2)が存在します。一方、日本の学校教育は9年間の義務教育の後、高等学校(3年間)に進学することが一般的です。
・学校年齢(入学開始年齢)
インドの学年は6歳から始まり、18歳まで続きます。日本では6歳から15歳までが義務教育の対象であり、高等学校教育を終えるのは約18歳から19歳です。
・教育カリキュラム
インドと日本のカリキュラムは異なり、インドの教育は地域や州によってカスタマイズされています。日本では国立基準に従った統一カリキュラムが採用されており、教育内容が全国的に均一です。
・言語
インドでは多くの言語が公用語として使用され、英語も広く話されています。一方、日本では日本語が主要な教育言語であり、英語は外国語教育として提供されています。
・試験システム
インドでは高校卒業後の大学入学試験(JEE、NEETなど)が非常に競争が激しいものとされており、試験の結果が大学進学に大きな影響を与えます。日本では大学入試も重要ですが、インドほどの競争がないことが一般的です。
・教育政策
インドと日本の教育政策は異なり、教育改革のアプローチや目標が異なります。日本では個々の学生の幸福と個人の発展に焦点を当てる一方、インドでは社会的な平等と多様性に関連した課題も強調されています。
インド(バーラト)の大学ランキング
インドには多くの優れた大学が存在しますが、その中でも特に評価の高い大学をランキング形式でご紹介します。
①インド工科大学ボンベイ校(Indian Institute of Technology Bombay)
②インド工科大学デリー校(Indian Institute of Technology Delhi)
③インド工科大学マドラス校(Indian Institute of Technology Madras)
④インド工科大学カンプール校(Indian Institute of Technology Kanpur)
①インド工科大学ボンベイ校(Indian Institute of Technology Bombay)
インド工科大学ボンベイ校は、インドで2番目に古い大学として知られています。1958年に旧ソビエト連邦の支援を受けて設立され、工学教育・研究分野で世界をリードしています。特に数学・情報科学の分野で有名であり、優れた人材を多数輩出しています。また、インドの共通大学入試のトップ100名のうち、70%がこの大学に入学していると言われています。
(参考)Indian Institute of Technology Bombay | IIT Bombay
②インド工科大学デリー校(Indian Institute of Technology Delhi)
インド工科大学デリー校は、1963年に設立された大学であり、最先端の研究と最新の教育プログラムが特徴です。バイオテクノロジー、土木工学、機械工学、コンピュータサイエンスなどの分野で優れた研究を行っており、世界的に評価されています。入学試験は非常に難関であり、トップクラスの学生が集まっています。
③インド工科大学マドラス校(Indian Institute of Technology Madras)
インド工科大学マドラス校は、基礎科学と応用科学の分野で国内で最も権威のある大学の一つです。1959年に設立され、ドイツ政府の支援を受けています。工学、理学の広い範囲にわたる研究を行っており、特に物理学部は高い評判を持っています。また、バイオテクノロジー産業においても多くの技術を生み出し、ビジネスリーダーを輩出しています。
(参考)Indian Institute of Technology Madras
④インド工科大学カンプール校(Indian Institute of Technology Kanpur)
インド工科大学カンプール校は、クリーンエネルギーや情報技術などの分野で世界的に評価されている大学です。環境に配慮した研究やエネルギー効率の改善に取り組んでおり、持続可能な未来の実現に貢献しています。また、コンピュータサイエンスや人工知能の分野でも優れた研究が行われています。
インド(バーラト)大学卒業生の就職事情
インドの優れた大学で学位を取得することは、将来の就職において大きなアドバンテージとなるでしょう。これらの大学は教育の質が高く、産業界でも高い評価を受けています。卒業生は世界各国の企業で活躍しており、特に科学技術や情報技術の分野での就職先が多いです。
インド工科大学などの一流大学の卒業生は、NASAやマイクロソフトなどの世界的な企業で働くこともあります。また、インド国内の優れた企業や研究所でも活躍の場を見つけることができます。就職の競争は激しいですが、優れた教育を受けた卒業生は多くの機会を手に入れることができます。
インド(バーラト)人の日本での就職
日本での雇用の可能性についても触れておくと、インドの大学で学位を取得した卒業生は、日本の企業や研究機関で働く機会もあります。日本は外国人材の需要が高まっており、留学生の採用や就職支援の取り組みも進んでいます。日本での就職を希望する場合は、日本語の能力や専門知識など、必要なスキルを磨くことが重要です。インドの大学で学んだ知識や経験を活かし、日本でのキャリアを築くことも可能です。
また、日本の法務省の在留外国人統計によると、2022年12月末時点で在日インド人は43,886人です。
在留資格別の在留インド人の人数(TOP5)
- 家族滞在:10,642人
- 技術・人文知識・国際業務:10,104人
- 永住者:8,318人
- 特定技能:6,132人
- 留学:1,851人
都道府県別の在留インド人の人数(TOP10)
- 東京 17,004人
- 神奈川 7,121人
- 千葉 2,196人
- 埼玉 1,926人
- 茨城 1,786人
- 兵庫 1,589人
- 大阪 1,566人
- 愛知 1,369人
- 北海道 1,104人
- 栃木県 1,033人
まとめ
インドの大学は世界的に評価されており、その中でも特にインド工科大学などの一流大学は優れた教育と研究を提供しています。これらの大学で学位を取得することは、将来の就職において大きなアドバンテージとなるでしょう。インドの大学で学ぶことは、世界的な視野を持ち、グローバルなキャリアを築くための重要なステップです。

大学ランキング2023】-人気大学と就職事情を紹介-jpg.webp)