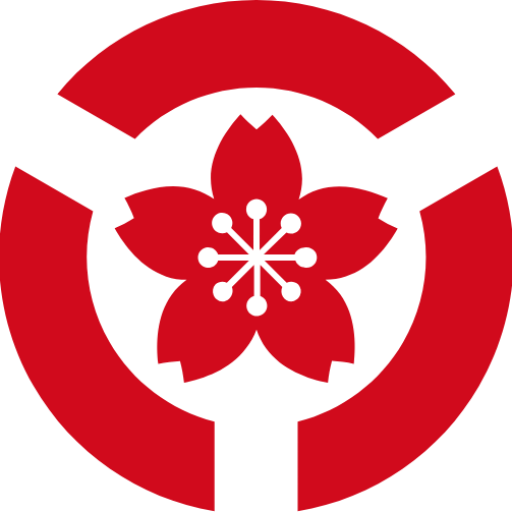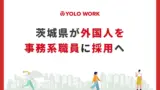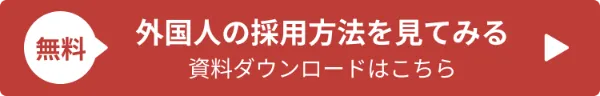三重県伊賀市は、2025年度の市職員採用試験(後期日程)において、県内の自治体で初めてとなる「外国人枠(事務職)」を設けることを発表しました。これまでも外国籍住民の応募は可能でしたが、日本語での筆記試験などが壁となり採用実績はゼロ。増加する外国人住民との「多文化共生」推進を目的としたこの新たな取り組みの詳細と、全国的に広がる外国人雇用の重要性について考えます。
三重県初!伊賀市が導入する「外国人枠」とは?
三重県伊賀市が、2025年度の市職員採用試験(後期日程)から、新たに「事務職〔多文化共生推進〕」として、外国籍の人材を対象とした採用枠を設けることを発表しました。
これは三重県内の自治体としては初めての試みとなります。
募集要項によると、この枠での採用予定人数は若干名。
応募資格として、学歴は問われず、日本の永住者または特別永住者の在留資格を持つ外国籍の方が対象となります。
伊賀市によると、この取り組みは「外国籍職員の視点を市政に活かし、誰もが暮らしやすい共生社会を形成し、全ての市民にとってより暮らしやすい伊賀市を目指すため」とされています。
ただし、採用された外国籍職員は、地方公務員法の規定に基づき、公権力の行使や公の意思形成への参画にあたる職(原則として管理職など)には就けないという制限があります。
背景にある課題:日本語試験の壁と多文化共生の必要性
伊賀市では、これまでも市職員採用試験において国籍要件を設けておらず、外国籍住民の受験も可能でした。
しかし、一次試験の教養試験や作文試験などが全て日本語で実施されるため、日本語能力が非常に高いレベルで求められ、結果としてこれまで外国籍職員の採用には至っていませんでした。
伊賀市の発表によると、市内人口のうち約7%が外国籍住民であり、多文化共生は市にとって重要な課題となっています。
多様化する住民ニーズに応え、全ての市民にとってより良い行政サービスを提供するためには、従来の画一的な日本語能力を前提とした採用試験だけでは、必要な視点や能力を持つ人材を確保しきれないという認識が、今回の「外国人枠」新設の背景にあると考えられます。
外国人採用の新たな動き:地方自治体の挑戦
人口減少や少子高齢化が進む日本において、外国人住民や労働者の存在感は年々増しています。
このような社会変化に対応するため、地方自治体が主体的に外国人材の採用に乗り出す動きは、非常に注目されます。
伊賀市の今回の取り組みは、単に人手不足を補うというだけでなく、行政サービスに多様な視点を取り入れ、外国人住民にとっても日本人住民にとっても住みやすい街づくり(多文化共生)を本気で目指すという意思の表れと言えるでしょう。
この動きが、他の自治体にも広がり、外国人材が活躍できる場が公的セクター(警察、国立や公立の学校等)にも増えていくきっかけとなるかもしれません。
広がる地方公務員への外国人採用の動き
伊賀市のような特定の「外国人枠」設置の動きだけでなく、地方自治体における外国人採用の門戸は他の形でも広がりを見せています。
例えば茨城県では、人口減少が進む中で外国人材の活躍が不可欠であるとし、「外国人材から選ばれる県づくり」を進める一環として、2026年度入庁(2025年募集開始)の事務職(大学卒業程度・高校卒業程度)採用試験から日本国籍要件を撤廃する方針を決定しました。
これにより、永住者や特別永住者の資格を持つ外国籍の方も、日本人と同様に一般の事務職を受験できるようになります。
ただし、伊賀市とは異なり、特定の「外国人枠」を設けるわけではなく、試験も日本語で実施されるとのことですが、一般行政事務を担う門戸を外国籍人材にも開いたという点で、画期的な動きと言えます。
このように、多文化共生の推進や多様な人材確保を目的として、地方自治体が外国人材の採用に向けて具体的な制度変更に踏み出す例が出てきていることは、今後の大きな流れを示唆しているのかもしれません。
まとめ
三重県伊賀市が県内初となる市職員の「外国人枠」を設けたこと、そして茨城県が事務職の国籍要件を撤廃したことなどは、多文化共生社会の実現と多様な人材確保に向けた地方自治体の具体的な動きとして注目されます。
これらは、増加する外国人住民への対応という側面だけでなく、多様な視点を行政サービスや組織運営に取り入れるという積極的な意義を持っています。
外国人材が持つ多様な能力や視点を活かし、彼らが地域社会や企業で活躍できる環境を整備することが、今後の日本の持続的な発展にとって不可欠な要素と言えるでしょう。