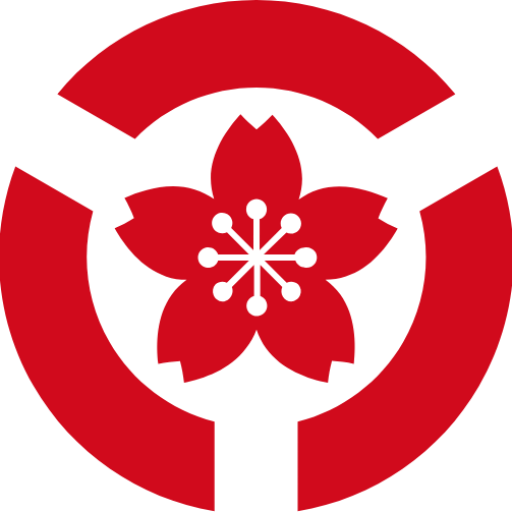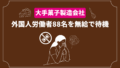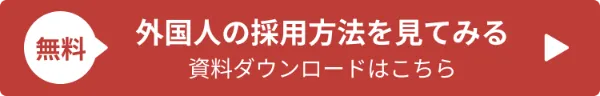出入国在留管理庁が初めて行った調査により、日本人の外国人受け入れに対する意識に、世代間で大きな差があることが明らかになりました。この記事では、外国人との交流経験の差が受け入れ意識に与える影響や、政府が目指す共生社会の実現に向けた取り組みについて紹介しています。少子化による人手不足が進む中、世代を超えて外国人と共に生きる社会のあり方に対する日本人の意識の現状と課題を考えるきっかけになります。
出入国在留管理庁が初めて行った意識調査により、若い世代では外国人の受け入れに好意的な意見が多いのに対し、高齢層では慎重な意見が目立つということが判明しました。
この意識の違いには、年代ごとの外国人との交流経験の差が影響していると考えられ、政府が目指す共生社会を実現するには、世代を超えた外国人との交流の場を増やしていくことが求められています。
出入国在留管理庁は、日本に住む外国人の意識調査は定期的に実施していますが、日本人を対象とした、外国人に対する理解度を調査するアンケート実施は今回が初めてです。調査は2023年10月〜11月に行われ、住民基本台帳からランダムに選ばれた18歳以上の日本国籍を持つ1万人を対象とし、有効回答数は4,424人でした。
地域社会で外国人が増えることについての質問では、全体の28.7%が「好ましい」と回答し、「好ましくない」と答えた23.5%をやや上回る結果となりました。特に年代別での違いが顕著となり、18〜19歳では半数以上が肯定的な回答するなど、40代前半までが外国人の増加に対して前向きな意見を持つ人が多くいました。一方で、高齢になるほど「好ましくない」「どちらとも言えない」と答える割合が増え、慎重な見方をする人が多い傾向にあることも明らかとなりました。
年代別による違いの一因として考えられるのは、外国人との交流経験の差です。
近年では、外国人労働者やその家族の来日が増加しているため、10〜20代では3人に1人以上が「通っている学校に外国人がいて、知り合いだ」と回答しています。学校生活を共に過ごした経験が、外国人の増加に対しての前向きな見方に繋がっていると考えられます。また、30〜50代の回答者の中には、「一緒に仕事をしている(していた)」と答えた人が3〜4割存在しました。
一方で、60代以上では学校や職場で外国人と接した経験が少なく、「外国人の知人はいないし、付き合ったこともない」と答えた人が4〜7割を占めていました。
国士舘大学の鈴木江理子教授(移民政策)は、「外国人との関わりが受け入れ意識に肯定的な影響を与えることは以前から考えられていたが、今回の大規模な調査でそのことで裏図けられた」と述べています。
少子化により深刻な人手不足が進む中、政府は外国人労働者の受け入れを拡大し、「共生社会の実現に向けた意識醸成」を目標に掲げています。鈴木教授は、「例えば交流イベントを開催する際には、イベント当日だけでなく、企画段階から外国人に参加してもらうなどして、対等な立場で継続的に交流を持つことが重要だ」と強調しています。



(参考)外国人受け入れ、若者は肯定的 入管庁が日本人初調査―日本経済新聞
年代によってこんなにも外国人受け入れ意識に差があるとは驚きです。今後、世代を超えた外国人との交流機会が増え、理解が深まることで、外国人受け入れを前向きに捉える人が増えることに期待したいです。