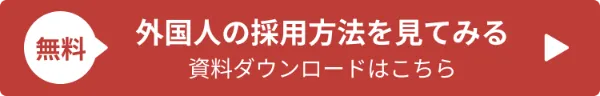業務形態の複雑性が増加する中で、意識せずに二重派遣が発生する事例が増えています。二重派遣には厳格な罰則規定が存在し、一部の状況では関係する全ての企業が罰則の対象になるリスクがあるため、注意が必要です。派遣元企業として、単に「知らなかった」や「気づかなかった」という理由では免れません。
この記事では、二重派遣を回避するための基本的な知識、罰則の対象となる可能性のあるケースとそうでないケース、具体的な罰則について詳しく説明していきます。

二重派遣とは
二重派遣とは、労働者を派遣元から派遣先A社に供給し、その後派遣先A社がさらに別の企業B社に同じ労働者を派遣する違法な行為を指します。この行為は、労働者の搾取を防ぐために法律によって禁止されています。
本来の派遣の仕組み
派遣の本来の仕組みは、派遣会社と雇用契約を結んだ労働者が、自社(派遣先)で働くサービスです。派遣の本来の仕組みでは、派遣労働者と派遣会社の間に雇用契約が存在し、派遣先企業は業務の指示を出す権限がありますが、雇用関係は派遣会社と労働者の間にあります。
・労働者は派遣会社と雇用契約を結び、派遣会社が派遣先企業に派遣労働者を派遣する。
・派遣先企業は、派遣労働者に対して業務内容を指示するが、雇用主は派遣会社である。
・給与の支払いや福利厚生に関しては、派遣会社が行う。
二重派遣の状態の特徴
二重派遣の状態には、以下の特徴があります。
1. 派遣元と労働者の雇用関係が存在する。
2. 労働者は派遣元から派遣先A社に派遣され、通常はA社で働くべきである。
3. 派遣先A社は、派遣労働者を別の企業B社に再び派遣する。
4. 派遣先A社は、B社から仲介手数料を得ている。
二重派遣が発生しやすい業界
二重派遣が発生しやすい業界として、情報技術(IT)分野と製造業が挙げられます。
IT分野では、多重派遣が問題視されています。この業界では、下請け企業が多数存在し、労働者を「常駐させる」という状況が頻繁に見受けられます。自社社員が指揮命令を行う場合は問題ありませんが、外部からの指示に基づいて労働者が働く場合、それは二重派遣とみなされます。
一方、製造業では、業務の需要が変動しやすいため、別の企業に作業員を派遣することがあります。これにより、労働者は別の企業からの指示の下で業務に従事することになり、これも二重派遣に該当します。
派遣先企業以外の関係者が派遣社員に業務指示を与える状況は、すべて「二重派遣」の事例として認識されるべきです。

二重派遣の禁止理由
二重派遣が禁止されている理由は、労働者の権利保護と適正な労働条件の確保を目的としています。ここからは、二重派遣が禁止されている主な理由を詳しく説明します。
・労働者の搾取防止
・雇用契約の透明性
・労働法の順守
・競争の歪み防止
・社会的安定と労働市場の健全性
要するに、二重派遣の禁止は、労働者の権利保護、雇用契約の透明性、法令順守、競争の公平性、労働市場の健全性を確保するための措置として設けられています。これにより、労働者と企業の双方にとって公平な労働環境が維持され、社会的な安定が促進されます。
労働者の搾取防止
二重派遣が許容されると、労働者が連鎖的に異なる企業に派遣され、その労働条件や給与が不透明になる可能性が高まります。最終的な派遣先での労働条件が劣悪であったり、適切な労働条件が確保されない場合、労働者は搾取されるリスクが高まります。禁止規定は、労働者の権利を守り、適正な労働条件を保証する役割を果たしています。
雇用契約の透明性
二重派遣が行われると、雇用契約の透明性が失われます。労働者と派遣会社、派遣先企業の間に複雑な契約関係が生まれ、誰が労働者の雇用主であり、どの条件が適用されるのかが不明瞭になります。透明性がないと、紛争や問題が生じた際に、労働者の権利を確保することが難しくなります。
労働法の順守
二重派遣が行われると、労働法に対する適切な遵守が難しくなります。異なる企業間で労働者が行き来する場合、どの法律が適用されるかが複雑になり、労働法の遵守が困難になります。禁止措置は、法的規則を明確にし、適切な法令順守を促進します。
競争の歪み防止
二重派遣が許容されると、企業は派遣労働者を安価で利用することができ、正規雇用の労働者と競争する際に不公平な競争が生じる可能性があります。これにより、正規雇用の労働者に不利益が及ぶおそれがあるため、競争の歪みを防止するために二重派遣が禁止されています。
社会的安定と労働市場の健全性
二重派遣は、労働市場の安定性を脅かす要因となります。労働者が頻繁に派遣元と派遣先を変更することは、労働市場の不安定さを増加させ、労働者の生活や職業の安定性に影響を与えます。労働市場の健全性と社会的安定を維持するために、二重派遣は制限されています。
二重派遣の罰則
二重派遣が許容された場合の法的な罰則規定について詳しく説明します。二重派遣は、職業安定法と労働基準法によって禁止されています。
また、厚生労働大臣からの行政処分のリスクも存在します。二重派遣を継続し、改善命令に従わない場合、厚生労働大臣から行政処分を受ける可能性があります。この際、企業名が公表されることもあり、企業の評判に影響を及ぼす可能性があります。
職業安定法による罰則
職業安定法の第44条によれば、以下のように規定されています。
【職業安定法 第44条】
何人も、次条(第45条)に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
つまり、二重派遣は、この労働者供給事業行為に該当します。なぜなら、派遣先企業と派遣社員との間に雇用関係がなく、支配関係のみが成立しているからです。職業安定法に違反すると、職業安定法第64条第9号に基づき、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。
労働基準法の罰則
労働基準法第6条には、「中間搾取の排除」に関する規定があります。
【労働基準法 第6条】
何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
つまり、この規定は、企業が他人の就業に介入して利益を得ることを禁じています。派遣先企業と派遣社員との間には雇用関係がないため、二重派遣はこの規定に抵触します。労働基準法に違反すると、労働基準法第118条に基づき、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
罰則を受ける対象
職業安定法第44条の違反に対する罰則の対象は、派遣先企業と再派遣を受け入れた企業です。ただし、再派遣先の企業が二重派遣の事実を知らずに受け入れた場合、罰則の対象とはなりません。しかし、二重派遣であることを認識したにもかかわらず、派遣社員を引き続き雇用していた場合、罰則の対象とされます。
一方、労働基準法第6条の違反に関しては、派遣社員を再派遣した派遣先企業だけが罰則の対象となります。
【職業安定法 第44条】
・派遣先企業
・再派遣を受け入れた企業
【労働基準法 第6条】
・再派遣した派遣先企業
どちらの場合でも、派遣された労働者には罰則が課せられることはありません。
二重派遣の事例
ここでは、実際に二重派遣が行われ、行政処分や検挙などの事件に至った事例を紹介します。
プロフェース・システムズ(2023年5月25日)
東京都中央区にある株式会社プロフェース・システムズは、法定の除外事由なしに労働者供給事業を行い、職業安定法第44条に違反したため、東京労働局から労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令が出されました。
これは、同社が派遣労働者を不適切に扱っていたことが原因です。東京労働局は、同社に対して行政処分を科し、労働者派遣事業の運営を改善するよう命じました。
また、労働者派遣法第14条第2項に基づく処分に違反した者には、職業安定法第59条第1項により、一年以下の懲役または百万円以下の罰金が科せられます。同様に、労働者派遣法第49条の規定による処分に違反した者には、職業安定法第60条第1項により、六月以下の懲役または三十万円以下の罰金が科せられます。
ただし、この情報が株式会社プロフェース・システムズに直接適用されるかどうかは明確ではありません。
(参考)派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令について |厚生労働省
櫻井精技、オオクマ電子、吉野電子工業、川上電装(2018年12月26日)
熊本県内の3つの労働基準監督署は、労働者供給事業から利益を得た企業、具体的には櫻井精技㈱(熊本県八代市)、オオクマ電子㈱(同県熊本市)、吉野電子工業㈱(同県玉名郡)、および川上電装(同県熊本市)の代表者ら6人に対し、労働基準法第6条(中間搾取)違反などの疑いで熊本地検八代支部と玉名支部に一斉送検しました。オオクマ電子と吉野電子工業は二重派遣を行い、川上電装の代表者は自身が責任者を務める企業の労働者を供給し、不当な利益を得ていたとされています。
(参考)中間搾取などで3社6人送検 労働者供給し利益得る 熊本・八代・玉名労基署|労働新聞 ニュース|労働新聞社
関東海陸企業、山樹(2018年5月22日)
神奈川労働局(局長:三浦宏二)は、港湾運送業において派遣が禁止されているにも関わらず、特定派遣事業主である関東海陸企業㈱(東京都港区)と㈱山樹(神奈川県三浦市)の2社に対し、6カ月間の事業停止を命じました。関東海陸企業は、自社の労働者を派遣するだけでなく、山樹から受け入れた労働者を派遣する「二重派遣」も行っており、派遣先で死亡災害が発生したことが問題視されました。
(参考)港湾運送業へ違法派遣 半年の事業停止命令 神奈川労働局|労働新聞 ニュース|労働新聞社
二重派遣とよく間違えられる「業務委託」「出向」との違い
業務委託とは
業務委託とは、特定の業務を他の企業や個人に委ねる契約形態です。業務委託には、通常「請負契約」と「準委任契約」という2つの主要なタイプがあります。
「請負契約」は、請負人が業務を完遂することを約束し、その成果に対して委託企業が報酬を支払う形態です。一方、「準委任契約」では、特定のスキルや知識・経験を持つ人に業務を依頼するもので、成果物を提出することを必要としません。この契約では、一定期間内で依頼者の業務をサポートし、代行するといった役割を果たします。
一般的に、業務委託においては、依頼者が直接的な指示権を行使することはありません。
出向(社内出向)とは
出向(社内出向)とは、企業が所属社員との雇用契約を維持しながら、関連する企業や施設での業務に従事させる手法です。社員は元の企業の籍にあり、給与の支払いについても元の企業が責任を負います。
業務の指揮権は、業務を行う出向先の企業が保持します。
ただし、派遣社員を別の会社に社内出向させることは違法です。指揮命令権を行使するのは社内出向先の企業であれば、雇用関係のない派遣社員を労働力として提供することになり、職業安定法第44条で禁止されている「労働者供給事業」に違反します。
まとめ
二重派遣は、労働者を派遣元から派遣先A社に供給し、その後A社が別の企業B社に同じ労働者を派遣する違法な行為です。通常の派遣では、派遣会社と労働者の間に雇用契約があり、派遣先企業は業務の指示を出す権限がありますが、雇用関係は派遣会社と労働者の間にあります。
二重派遣の特徴は、派遣元と労働者の雇用関係が存在し、労働者はA社に派遣され、A社がB社に再派遣することです。情報技術(IT)分野と製造業は二重派遣が発生しやすい業界であり、二重派遣は労働者の搾取を防ぐために禁止されています。
禁止理由は、労働者の権利保護、雇用契約の透明性、労働法の順守、競争の歪み防止、社会的安定と労働市場の健全性の確保です。罰則規定により、二重派遣を行う企業や再派遣を受け入れた企業は行政処分や罰金を受ける可能性があります。関連する事例も紹介されています。
業務委託や出向とは異なり、二重派遣は雇用関係や指揮命令権の問題から区別されます。